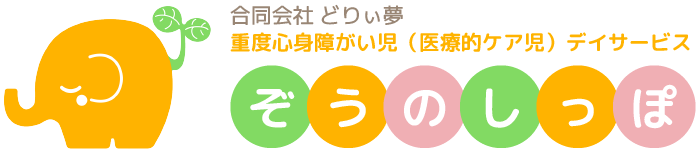事業内容service
 重度心身障がい児特化型
重度心身障がい児特化型
利用対象者
| 重症心身障がい児 | 重症心身障がい児(以降、重心児)は、重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態です。 症状は個人差がありますが、ほとんどは寝たきりで自力での移動が難しい状態、また自力での排泄や固形の食事を摂ることが難しいケースが多くなります。 |
|---|---|
| 医療的ケア児 | 医療的ケア児(以降、医ケア児)は、人工呼吸器などの医療機器や経管栄養やたんの吸引といった医療処置などを日常的に必要としている児童のことです。知的な遅れは必ずしも併発するわけではなく、医療的ケアを必要としている以外、他の児童と同様に、話したり授業を聞くことができる児童もいます。 |
| 重症心身障がい 医療的ケア児 |
重度心身障がい児の症状が進行し、経管栄養などの医療的ケアが必要になってくると「重症心身障がい医療的ケア児」(以降、重心医ケア児)に該当する可能性があります。 重心児医ケア児に対しては、身体介助に医療的ケアと複合的なサービスの提供が必要になります。 |
概要
定員5名の少人数体制により、複数のスタッフで充実した療育をおこなうことができます。
全身状態の観察や希望により入浴、心身を活性化するための活動(創作やレクリエーション)を個々の体調に合わせて行っていきます。医療的ケアも行います。
サービス内容
重心児の心身の健康状態や病状などを観察したうえで、個別に必要なケアを行います。
- 呼吸の管理
- 吸引、吸入、酸素吸入、人工呼吸器など呼吸の管理
- 食事の管理
- 経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろう、摂食嚥下訓練、食事の介助
- 薬の管理
- 服薬の介助、軟膏の塗布など
- 生活介助
- 療養の世話、排泄ケア、入浴介助、清拭、更衣、機能訓練など
その他のサービスは、一般の放課後等デイサービスと同様に活動し、リハビリやコミュニケーションを促すような療育や機能訓練を提供します。
※医療的ケア児の受け入れにより、サービスの内容が異なります
 発達支援
発達支援
目的
- 児童発達支援2歳~5歳までの未就学児
- 児童発達支援は、個別療育とグループ療育を実施していきます。個々の子どもそれぞれの良さを発揮できる場所を提供し、人と関わる力の向上を目指します。
医療的ケア
医師の指示のもと、経管栄養や吸引、呼吸器の管理を看護師が実施します。
- 一般状態の観察
- 呼吸管理
- 気管カニューレ、吸引、吸入、酸素吸入、人工呼吸器、気管切開など
- 食事管理
- 経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろう、摂食嚥下訓練、食事の介助
- 薬の管理
- 服薬の介助、軟膏の塗布など
- 療養の世話
- 排泄ケア、入浴介助、清拭、更衣、機能訓練など
基本的なケア
- 1健康・生活
健康状態の把握、リハビリテーションの実施 -
- 子どもたちの様々なサインから心身の異常に気付けるように観察をおこないます
- 身の回りを清潔にし、生活に必要な基本的技能を獲得できるように支援します
- 2運動・感覚
姿勢と運動、動作の向上、保有する感覚の統合的な獲得 -
- 姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善および習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図っていきます
- 保有する感覚を十分に活用できるように、遊びなどを通して支援します
- 3認知・行動
認知の発達と行動の習得 -
- 物や空間、時間などの概念の形成を図ることで、認知や行動の手がかりとして活動できるように支援します
- 4言語・コミュニケーション
人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 -
- 具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつけるなどにより、体系的な言語の習得を促します
- 言葉や絵・記号などを用いて相手の意図を受容し、自分の考えを表出する支援を行います
- 様々なコミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達が円滑にできるように支援します
- 5人間関係・社会性
他者との関わりの形成、仲間づくりと集団への参加 -
- 人との関係を意識、その信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成するための支援を行います
- 大人を介在して、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援します
 放課後等デイサービス
放課後等デイサービス
目的
- 放課後等デイサービス
6歳(小学校1年生)~18歳(高校3年生) - 日常生活の活動の中でのルール、社会生活を送るうえでの約束を知り、自立して生活できるようになるための療育を行うことを目的とします。
医療的ケア
- 一般状態の観察
- 呼吸管理
- 気管カニューレ、吸引、吸入、酸素吸入、人工呼吸器、気管切開など
- 食事管理
- 経鼻経管栄養、胃ろう、腸ろう、摂食嚥下訓練、食事の介助
- 薬の管理
- 服薬の介助、軟膏の塗布など
- 療養の世話
- 排泄ケア、入浴介助、清拭、更衣、機能訓練など
基本的なケア
- 1健康・生活
健康状態の把握、リハビリテーションの実施 -
- 子どもたちの様々なサインから心身の異常に気付けるように観察をおこないます
- 身の回りを清潔にし、生活に必要な基本的技能を獲得できるように支援します
- 2運動・感覚
姿勢と運動、動作の向上、保有する感覚の統合的な獲得 -
- 姿勢保持や上肢・下肢の運動・動作の改善および習得、関節の拘縮や変形の予防、筋力の維持・強化を図っていきます
- 保有する感覚を十分に活用できるように、遊びなどを通して支援します
- 3認知・行動
認知の発達と行動の習得 -
- 物や空間、時間などの概念の形成を図ることで、認知や行動の手がかりとして活動できるように支援します
- 4言語・コミュニケーション
人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得 -
- 具体的な事物や体験と言葉の意味を結びつけるなどにより、体系的な言語の習得を促します
- 言葉や絵・記号などを用いて相手の意図を受容し、自分の考えを表出する支援を行います
- 様々なコミュニケーション手段を活用し、環境の理解と意思の伝達が円滑にできるように支援します
- 5人間関係・社会性
他者との関わりの形成、仲間づくりと集団への参加 -
- 人との関係を意識、その信頼関係を基盤として、周囲の人と安定した関係を形成するための支援を行います
- 大人を介在して、自分の行動の特徴を理解するとともに、気持ちや情動の調整ができるように支援します
その他
- コミュニケーション
- 会話、本の読み聞かせ、テレビやCDなどの視聴覚教材の活用、レクリエーション、制作活動、散歩、交流会の開催など
- 家族支援
- 就学相談、障がい受容などの情報提供、家族会、親同士の交流の場の提供、きょうだい児への支援、医療福祉制度の情報提供と利用援助など
- 地域連携
- 地域の市役所、学校、相談支援員などとの連携を行う
- 連携会議開催
- 自治会長、民生委員・児童委員、家族、委託医との連携会議を開催
- 年間行事
- 誕生日会、七夕、クリスマス、花見会、保護者会など